| エリファス・レヴィへの転身 |
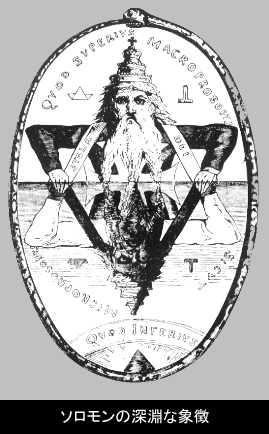 |
コンスタンがエリファス・レヴィを名乗った翌年の1854年、彼は英国に渡り、小説家で英国薔薇十字会員でもあったブルワー・リットン卿とロンドンで知り合う。レヴィはリットン卿を、彼の小説『ザノーニ』(1842)の内容から英国に於ける隠秘学研究の第一人者とみなしていたようである。だがロンドンで出会ったその他の人物は、レヴィにとって益するところは無かったようである。『高等魔術の教理と祭儀 教理編』では次のように書かれている。しかしその中の幾人かと出会ってみた結果は、すこぶる丁重な応対とは裏腹の無関心か、それともたんなる興味本位の地金を見せつけられるだけに終わった。まるでべてん師でもあしらうみたいに、その場でいきなり私にむかって奇蹟を要求するのである。少々がっかりさせられた。(1) |
ロンドンでは、レヴィ自身は魔術の儀式を実践するつもりはなかったようである。しかしリットン卿を介しての頼みによりネクロマンシーの儀式を行うことを承知し、テュアナのアボロニウスの招魂を行う。アボロニウスの出現の様子は次のような次第である。
煙が拡がり、炎は照らし出すすべてのものを揺らし、やがて消えつきた。大理石の祭壇の上に煙が白くゆるやかに立ち昇ると、私は足もとの地面が揺らぎだすように思え、耳が鳴り、心臓が激しく動悸を打った。もう一度焜炉に枝と香料をくべ、そして炎が立ちのぼったとき、祭壇の前に、はっきりと、並みの背丈よりも大きな一人の人間のかたちがほぐれて、消え去っていくのが見えた。 (2) 一回目は出現しただけ何の会話もできなかったため、彼はもう一度儀式をやり直す。再び霊が出現し始めた時、レヴィは目をつぶってアボロニウスの名前を呼んだ。そうすると彼が目を開いた時には、「一人の男が、白というよりもむしろ灰色に見える屍衣のようなもので全身くて、私の前にいた」(3)ということである。 英国から帰ったレヴィは、フランスに薔薇十字団を再建し、l856年には『高等魔術の教理と祭儀 教理編』を出版する。さらに1860年には『魔術の歴史』、1861年には『大神秘の鍵』と、エリファス・レヴィの巌も重要な部作が刊行される。 この三部作は、この世のー切を統一する原理を説明し尽くそうという意図のもとに、周到に計画された書物である。『魔術の歴史』の序文には、次のようにその意志が明確に述べられている。 古き魔法道士の科学に関するエリファス・レヴィの所業は、三部に分たれた完璧な講義集を形成するだろう。その第ー部は『高等魔術の教理と祭儀』であり、第二部は『魔術の歴史』であり、第三部はのちに出版さるべき『大神秘の鍵』である。 (4)三部作という形は、カバラの数の理論に厳密に基いたものである。つまり、「完全な言は三よりなる、けだしそれは知的原理、語る原理、そして語られる原理を前提とするからだ」(5)とあるように、一つの絶対的なものを表わすためには三という形が必要なのである。 そしてそれぞれの著作も全てその数の理論に基いている。『高等魔術の教理と祭儀』は、十三の教義と九つの信仰を表わす二十一個のカバラ的アルファべットと正確に対応するように章分けがなされている。『魔術の歴史』では、三と四とが結合し「魔術的ちからが全力を発揮したかたちを表わす」(6)という数、七に基いている。そして『大神秘の鍵』では、「魔術の大秘奥」を象徴する統一された三、つまり四という数に基くことによって三つの著作の統合の意味をも持たせている。 この三つの書物は当時の文化人たちを中心とする人々に大いに受け人れられ、十九世紀末のフランスに於けるオカルティスムの復興へとつながって行く。その基盤となる精神的状況を、コリン・ウィルソンは『オカルト』のなかで次のように指摘している。 「十九世紀人は唯物論的で退屈な世界に難破している自分自身を見出した。中世においては、悪魔は誰もが疑問をもたずに受け容れた現実であった。従って、テヨビロ伝説が病的な魅惑を呼び起こしたのである。今や影は去り、ありふれた日中の光があらゆるものを強固な、はっきりしたものと化せしめた。そしてロマン主義老たちは、鉄道や外車蒸気船よりも遥かに想像力にとって刺戟のある悪魔や夢魔の時代を郷愁の眼をもって振り返ったのである。 (7)そういった時代状況のなかで、“魔術とは何か?"という問いに対して初めて近代的精神の立場から答えたのがエリファス・レヴィであった。それは宗教と対立することもなく、それまでは部分的にしか紹介されてはいなかった様々な事項について、一貫した論理的体系を打ち立てたものである。 多くの文学者を魅了した書ではあったが、半ば近親憎悪のようにユイスマンスには酷評された。彼は次のようにレヴィの書を評価している。 すなわち彼は、はじめは荘重な口調で古来の奥義を明らかにしたいといっているが、いざその場になると、もしもそのような怖ろしい秘義をあばいたら、一身の破滅を招くことになるだろうという不思議な口実のもとに、まったく口を閉ざしてしまう。 (8)もちろんこの評価は誤ってはいない。レヴィは秘密が確実に存在することを証明してはいるが、その秘密を開示することは決してしてはいないのだ。だがそれは当然のことである。自ら秘密を解き明かせない者に、秘密を教えることは害悪となるだけである。 つまり、ランボーやボードレール、マラルメからブルトンに至る文学名たち、そして数多くの隠秘学者たちを魅き付けたものは、ユイスマンスの言うような表面的なものではないのである。 真にレヴィが放つ魅力とは、レヴィの生れ変わりであると自称する魔術士アレイスター・クロウリーの指摘する次のような点であろう。 たったひとつの文章の中に、崇高さと熱意とが、嘲笑的な苦渋・懐疑・粗野。侮蔑とを混淆しているのだ。可能な限り多くの対立要素からなる不協和音を打ち鳴らすのは、正しく歓喜の極みである。その歓喜は、力の感覚-ありとあらゆる思考の要素を霊感的な創作に貢献させる力-を満たすことから抽き出されるように思われる。 (9) |
| * |
|
1861年レヴィは再びロンドンを訪れ、当時英国に逃れていた慈善カルメル会の教祖ウジェーヌ・ヴァントラスと出会う。ヴァントラスはフランスで悪魔崇拝の教会をつくり、黒ミサなどを行っていた人物であり、ローマ法王庁からの異端の宜告によって国外追放となっていたのである。 ヴァントラスのほうはレヴィに共感の言葉をもって接したのであるが、レヴィのほうは彼をたんに通俗的な妖術師としかみなさなかったようである。レヴィは基本的に魔術哲学を究めようとしたのであり、儀式魔術に関しては否定はしないが、その段階にとどまっていたのでは絶対的な知を見出すのは難しいと考えていたようである。それは後年マンリー・P・ホールが述べている次ような態度であろう。 超越魔法およびあらゆる種類の幻術魔法は袋小路に過ぎない。それはアトランティス的妖術の末裔である。哲学の大道を捨ててそこにさまよい込んだものは、大抵例外なくその愚行の犠牲者になってしまう。人問は自分自身の欲望を制御できなければ、激しくも荒々しい自然霊たちを支配するという仕事はとうてい不可能なのである。 (10) 勿論真の道士となり得たときには、儀式魔術の全てをも自在に活用することは出来るであろう。しかしその域に達するまでが問題なのであり、好奇心を満たすという人間的な欲望がどうしても介在してしまう儀式魔術の'実践からは道士に達するのは非常に困難なことなのである。 その後もレヴィは、数多くの彼の信奉者たちとの交際を受け人れるが、彼にとっては皆低俗な妖術師ばかりであり、軽蔑の念しか抱かせはしない者たちであった。それでも彼は自分の研究を深化させて行き、1862年には『神話と象徴』、1865年には『聖霊の科学』などを出版する。 そして彼の死後の出版とはなったが、1868年にはカバラの最も重要な教典である、『セフェール・ハ・ゾハール』の注釈書を仕上げる。 エリファス・レヴィの晩年は悲惨な生活を強いられていたようである。それは彼が妖術使には決してならなかったということの証しでもある。貧困のなかで、しかし魔術を信じて、1875年に六十五歳でこの世の存在という一形式を捨てた。 |
